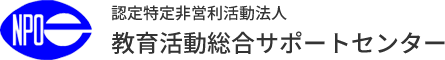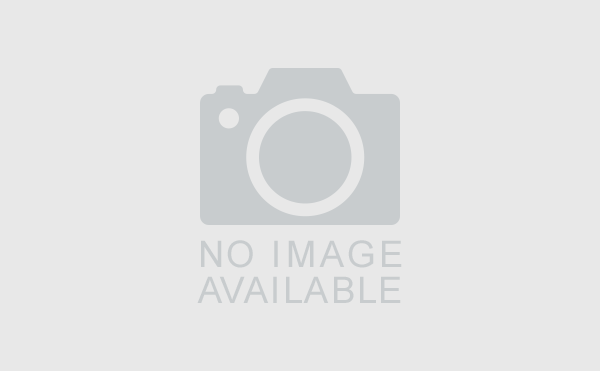第1回研究協議会開催
6月20日(金)午後2時から川崎市教育会館で今年度初めての研究協議会が川崎市教育会館で開催されました。

サポートセンターでは、設立以来20数年にわたり「不登校にかかわる研究」を継続して行っている珍しい団体です。
今年度は、「子どもの声から不登校を考える」というテーマの研究のまとめの年になります。
しかし、サポートセンターの研究をよく調べてみると、実は「子どもの声から」という内容は、実に7年にも及ぶ研究となっているのです。
それだけ、「子どもたちの声を聞いて、その声を子どもたちの多様な支援に生かしていく」という営みは、とても難しい面をもっているということなのだと思います。

「子どもの声を聞く」と言っても、どう聞けばよいのか、子どもを傷つける恐れはないのか、聞いたことをどう受け止めていけばいいのかなど悩みはつきません。また、子どもたち一人ひとりの思いは多様であり、一人ひとりの子どもの考える「最善の利益」と、おとなの考える「最善の利益」が食い違う面が常にあります。
今年度、研究サブテーマを「~子どもの多様な学びに寄り添う支援のあり方~」として新たに設定しました。ここで言う「学び」とは、学習指導要領に準拠した「学習」という狭い解釈ではなく、子どもたちから「学びたい」と声を発した「学び」であり、「支援」とは子どもたちの一人ひとりの思いを受け止め、その思いに寄り添っていく「支援」と考えています。折しも、文部科学省のほうでも「不登校特例校」という名称が「学びの多様化学校」と変化してきました。子どもたちの求める多様な「学び」を保障する営みが学校でも求められている時代になったとも言えると思います。
この研究の報告会は、令和8年2月14日(土)午後2時から武蔵小杉にある「生涯学習プラザ」で開催する予定です。是非、興味のある方は奮ってご参加ください。また近くになりましたら、チラシやホームページからご案内いたします。